きのこ×フロンティア
第17回「Mycologist needs buddy/body.」
2024.03.26 Tue
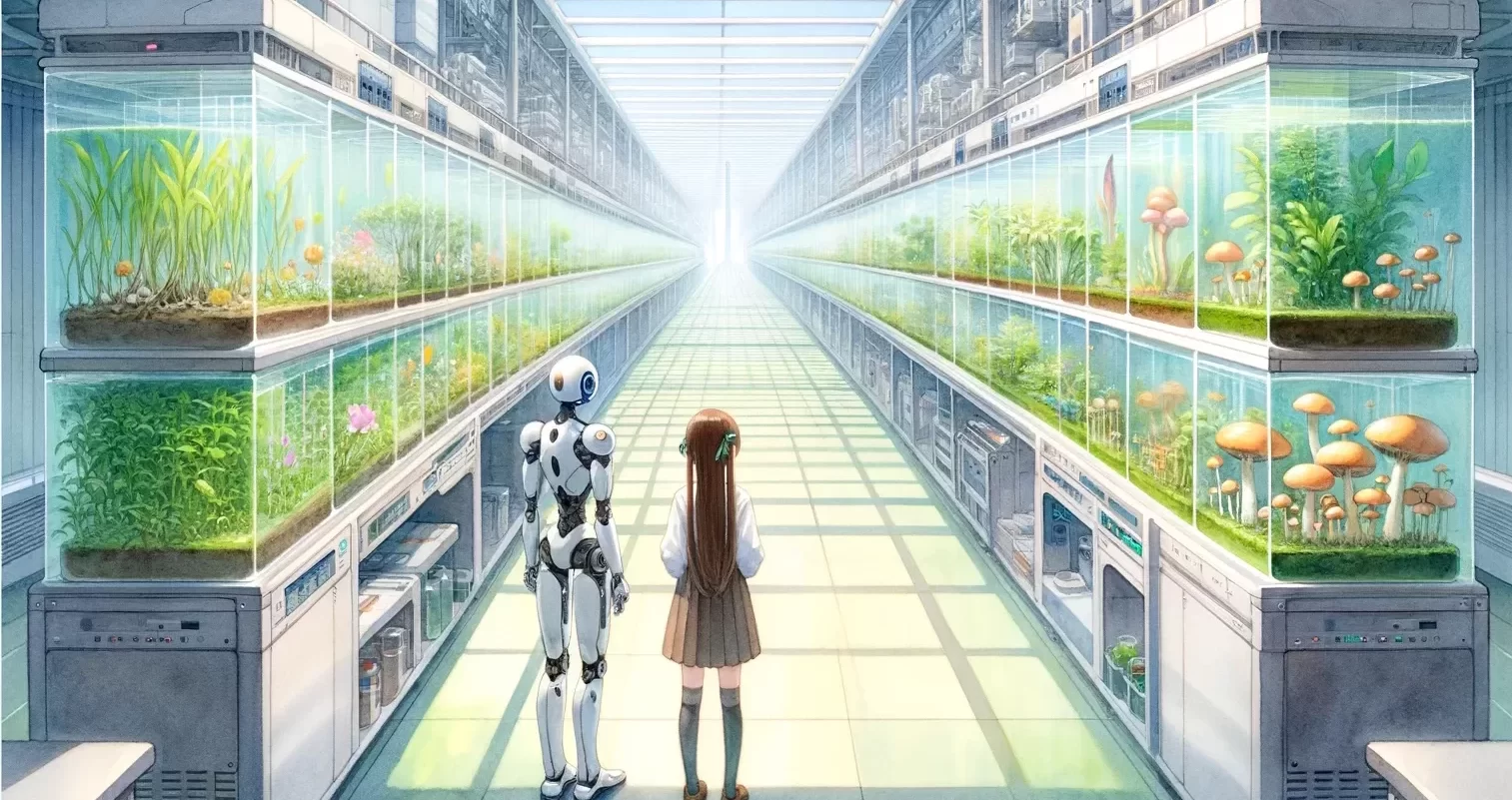
前回の記事では大規模言語モデル (LLM) が世界を急速に変革しつつある状況を踏まえ、それを菌類学における「同定支援エージェント」として利用できるかという論点を取り上げました。その後半年が経ちましたが、社会における生成AIの活用はさらに拡大傾向にあり、その勢いはまさに留まるところを知らない状況です。菌類学の分野では、LLMが同定に限らず野外調査、実験計画、論文執筆など様々な場面で活用されることが見込まれ、実際にその恩恵を受けた研究成果も(それが明示されているとは限りませんが)既に世に出始めていることは確実だと思われます。しかしながら、これほどLLMが普及しても、現状ほとんど到達できていない「ステージ」があります。それは、「現実世界における人間とLLMとの物理的協働」です。今回の記事ではこのテーマに焦点を当て、菌類学の未来を展望してみたいと思います。
2024年3月に発表された「Figure 01」というロボットは、Figure社とOpenAI社が提携して開発した「ChatGPT搭載ロボット」として注目を集めています。Figure 01のデモ動画では、ロボットが人の言葉や周囲の環境を理解して自然な会話や動作(リンゴを手渡す、お皿を片付けるなど)を行うだけでなく、その結果のフィードバックを受けて現状を推論し、さらに自律的に次の行動に繋げる能力が示されていました。ここまでハイレベルな柔軟性と適応性を見せつけられると、いよいよ汎用人工知能 (AGI) ロボットの実現も遠くないのではないかと感じさせられます。そして、この段階に至ると、これまでLLMの用途について長らく思案し続けてきた私たちも、発想を「コンピュータの中 (in silico)」からその外側へと解放させる必要があるかと思います。
しかし、仮に対話型AIロボットが現実世界への物理的介入を可能にしたとしても、高価で貴重なロボットを、風雨や塵埃など様々な障害のある野外で運用するのはハイリスクであり、とりわけ菌類学における「フィールド」は田畑や果樹園のような管理された環境とも通常は程遠いので、現段階では実現性は低いかと思います。やはり、まずは安定した環境である実験室内の運用を考えるのがよいでしょう。ラボ・オートメーション(研究室の自動化)にはLLMの登場以前から様々な手法が検討されていますが、通常高価な機器を必要とし、分類学のように予算面で常に制約の多い分野や、ましてや筆者のようなアマチュアによる「DIYバイオ」の現場からは到底手が届かないのが現実です。菌類分類学の研究室では、培地の調製や菌株の分離および移植、顕微鏡観察など大半の作業が人手で行われており、時間的にも労力的にも大きな負担となっています。対話型AIロボットはここに革命的な変化をもたらすことができるでしょうか?
ところで筆者は先日、アメリカのアマチュア研究者が主催する2日間の「ナノポアシーケンシング講座」をオンラインで受講しました。ナノポアシーケンシングは第7回の記事で名前だけ登場しましたが、従来とは桁違いの低コストでDNAの塩基配列データを取得することができる革新的な技術です。この技術を使用したONT社の代表的な製品「MinION(ミナイオン)」は、従来の機器が巨大な据え置き型で数百万円~数千万円の価格であるのに対して、手のひらサイズかつ1回10万円程度で使用することができる画期的なデバイスです。講師のS・ラッセル氏は長年かけてこれを用いたプロトコルを確立し、北米産のきのこのDNAを大量に取得できる体制を整えてきました。もはやDNAデータがないと分類学的議論ができないと言っても過言ではない現代菌類学において、一般市民でも手が届くこの技術はぜひとも日本に「輸入」したいところであり、その実現が急務だと考えています。

Oxford Nanopore Technologies公式ホームページ(https://nanoporetech.com/resource-centre/flongle)より引用。
しかし、実際に講座を受けてみると、まだ「誰でも手軽に実践できる」という段階には遠いように思われました。その理由の一つが実験操作の複雑さです。ナノポアシーケンシングでは一度に数百個のきのこ標本を処理し、最終的にほんの1つの小さなチューブにサンプルを集約させます。いわば、様々な種類のきのこから抽出したDNA入りエキスを混ぜて、一口分にも満たない量の「スープ」を作る作業だと思ってください。そのスープの数滴分をMinIONに充填(ロード)することで、内部でDNAの配列決定(シーケンシング)とともに自動選別を含む複雑な処理(デマルチプレクシング)が行われます。このプロトコルでは大量のサンプルに対する精密かつ繰り返しのピペッティング操作が求められ、サンプル間で汚染が起こったり、元の標本とサンプルとの対応関係が分からなくなったりしてしまうと、全体が台無しになってしまうというリスクもあります。ラッセル氏は既にこの問題を認識し、300万円以上する液体ハンドリングロボットを導入することで解決していました。このロボットは、予め入力された設定に基づき、アームでピペットを掴み、使い捨てチップを取リ付け、正確な量の液体を吸引し、目的のチューブに分注し、チップをゴミ箱に廃棄するという一連の動作を自動で行います。講座のお昼休み(日本は深夜!)の間、このロボットがせっせと作業するのを眺めていたのですが、あたかも未来の光景を目の当たりにしているかのようでした。

「ONT MinIONによるDNAバーコーディング講座 (https://mycota.com/product/dna-barcoding-with-ont-minion-course/)」で実際に使用されていたロボット、「OT-2」液体ハンドリングシステム。
この液体ハンドリングロボットに対話型AIが内蔵されたとすると、可能性は大きく広がるでしょう。研究者は複雑なプログラムを設計しなくても、例えば「10 μLずつ96ウェルプレートに分注せよ」といった自然言語でロボットに適切な動作を行わせることができます。AIが実験計画を自律的に最適化したり、実験中生じた問題に対して解決策をその場で特定して実行することも可能かもしれません。さらには重量センサー、カメラ、pH計、マイクロ流体チップ、バーコード・RFIDによるサンプル追跡など、他のオートメーションシステムを統合し、単なる分注作業のサポートを超えた「知的な実験アシスタント」として振る舞ってもらうことも可能になるかもしれません。実験の一部始終はロボットの内部に記録されているので、データの整理や品質管理のほか、解析や可視化も容易になり、研究者はより高度な判断や、創造的で付加価値の高い仕事に注力することができるはずです。
ただし、どれだけAI技術が発達しても、その恩恵が享受されるかどうかは人間側のリテラシーにかかっていることは強調しておきたいと思います。実は、DNA抽出作業の一部を行うロボットは筆者が学生の頃から存在しており、ある大学の研究室を見学した時にそれを初めて見たのですが、驚いたことに、その最新鋭のロボットを学生は使わせてもらえないとのことでした。手作業とコストが大して変わらず、操作ミスや雑菌の混入、怪我やバイオハザードの危険性なども軽減できるにもかかわらず、単に「学生は楽せずに苦労するべき」という考えでそうなっているのだとしたら、それは明らかに時代遅れの謗りを免れないと思います。
筆者は少なくとも、DNAの抽出から配列決定までの一連の流れに限っては、「実験」ではなく単なる「作業」だと考えています。もちろん、その背後にある手技や原理についてはしっかりと理解しておく必要がありますが、数年という短い期間(卒業研究は1年!)で成果を出さなければならず、絶対的に時間が足りない学生こそ、単調で反復的な作業はロボットの支援を受けるべきではないでしょうか。研究のために食事を摂らなかった、徹夜した、研究室に寝泊まりしたというのはしばしば「武勇伝」や「美談」になりますが、見方を変えれば単なる長時間の無償労働という面もあり、多くの学生がメンタルヘルスに支障を来しているのが現状です。その上、その「作業」に自分の身を捧げた分だけ、貴重な学生時代に高度な専門知識や技能、あるいは専門外の経験に触れたり、社会との接点を持ったりする機会が失われることになります。教育者・指導者側の意識改革も求められていると思います。
最後に、LLMの進歩により、対話型AIロボットが登場してラボ・オートメーションが飛躍的に拡大する未来はそう遠くないと思われますが、これに伴いコスト面でも好ましい変化が起こることが十分ありうると思います。具体的には、汎用性の向上が大量生産によるコストダウンをもたらす可能性があるほか、ロボットの制御ソフトウェアのオープンソース化などによっても、ロボットが研究機関のみならず教育機関や個人の手に届く存在になることが十分ありうるでしょう。菌類学の健全な発展には、この時流を把握して新技術を積極的に取り入れるとともに、従来の慣習にとらわれない柔軟な発想を持つことが必要ではないかと思います。
第17回「Mycologist needs buddy/body.」
2024.03.26 Tue /
第16回「ふわふわとがっちりの狭間で」
2023.07.06 Thu / 中島 淳志
第15回 「generation」
2023.01.11 Wed /
第14回:「i am Naturalist」
2022.06.03 Fri / 中島 淳志
第13回:「想い」が背を押す
2021.11.30 Tue / 中島 淳志
第12回:saturation
2021.05.12 Wed / 中島 淳志
第11回:雲と安楽椅子
2020.11.04 Wed / 中島 淳志
第10回:無免行路
2020.01.07 Tue / 中島 淳志
第9回:フロンティアの空白地図
2019.10.01 Tue / 中島 淳志
第8回:憧憬のクライテリア
2019.07.08 Mon / 中島 淳志
第7回:同定は「先ず解より始めよ」?
2019.05.28 Tue / 中島 淳志
第6回:ハイスループット・フィールド・フェノタイピング
2019.04.25 Thu / 中島 淳志
第5回:きのこ×ヴァリアンス
2019.03.26 Tue / 中島 淳志
第4回:きのこ×ディスタンス
2019.02.26 Tue / 中島 淳志
第3回:根拠に基づくきのこ採集(EBM)
2019.01.22 Tue / 中島 淳志
第2回:命懸けの同定
2018.12.26 Wed / 中島 淳志
第1回:序論
2018.11.13 Tue / 中島 淳志



