きのこ×フロンティア
第2回:命懸けの同定
2018.12.26 Wed

私がこれまでの人生で得た教訓の一つとして、「何か新しいことを始める時には、それに命懸けで取り組んでいる人に学ぶべし」というものがあります。戦争が科学技術の発展を推進してきたとはよく言われることですが、その是非は別として、洗練された技術は、しばしば命懸けの逆境から生まれるものです。例えば、絶対にほどけない紐の結び方を学びたいのであれば、高所作業員やロッククライマーのやり方に学ぶべきでしょう。深海で、高山で、宇宙で、たった一つのミスが命取りとなる生死の境を切り抜ける手段は、それぞれの極限に挑む人たちこそが共有しています。そして、磨き上げられたベストプラクティスの結晶が技術となり、やがて学問の体系に組み込まれていくのではないかと思います。
私は「いかに正確にきのこの名前を同定するか」という命題に対して、まずそれがそもそもどのような行為なのか、という一般化を試みました。前回の記事では生物の同定を、「目前にある未識別の事物・事象が果たして既成の分類のどの部分に位置づけられるのか、あるいはそれに当てはまらない場合、どの部分に最も近しいのかを追究する行為」と定義しましたが、我ながらこの定義は程よく一般化されていると思います。この行為をアナロジー思考でできるだけ「命懸けのベクトル」に寄せていった時、私が辿り着いた答えは「医学における診断」でした。
生物学に「同定学」という分野は(少なくとも筆者が知る限り)ありませんが、医学において「診断学」は確立された一分野です。生物学の研究者たちはもちろん、正確な同定を目指して生き物と日々真摯に向き合っていますが、通常は誤同定に明確なペナルティが存在することはなく、誤同定の責任を取って腹を切った、という話もさすがに聞きません。そしていずれ後述する通り、実は専門家による同定結果は、技量だけでなく構造的な問題も関連し、無謬とは程遠いのが現状です。一方、疾患の診断はたった一つのミスが患者の生命、あるいは「医師生命」の喪失に直結しうる行為であり、医師のみが行うことができる「絶対的医行為」と見なされることにもその重大さが表れています。きのこに限らず、生物の同定そのものが研究対象となることは稀だと思いますが、仮にそれを将来「同定学」に昇華させるならば、「命懸けの状況」で発展してきた医学の診断に関する知見は、偉大なベンチマークとなりうるのではないかと考えています。
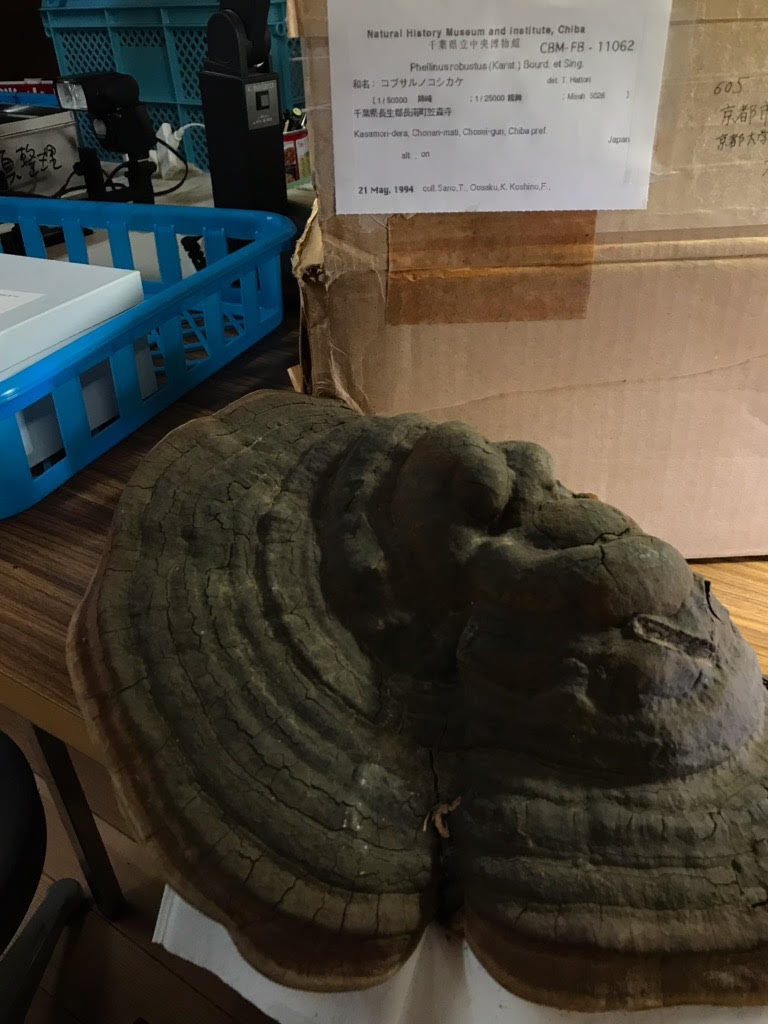 医学における根拠(エビデンス)のレベルは、しばしばピラミッドのような階層構造で図示されます。このピラミッドの具体的内容には様々なバリエーションがあるようですが、専門家や権威者の意見や考えが下層(しばしば最底辺)に位置付けられる傾向は一致しています。私はこの図を初めて見た時、感銘を受けると同時に、ある種の慄然とした感情を覚えました。「この学問は、この答えに辿り着くまでに一体どれほどの犠牲を払ってきたのだろう?」という考えが脳裡を去来したのです。事実、ルネサンス以前の西洋医学ではガレノスが絶対的権威として、数百年もの間「ピラミッドの頂点」に君臨してきたのですから、学問の発展によって価値観の顛覆が成し遂げられたのは確かです。
医学における根拠(エビデンス)のレベルは、しばしばピラミッドのような階層構造で図示されます。このピラミッドの具体的内容には様々なバリエーションがあるようですが、専門家や権威者の意見や考えが下層(しばしば最底辺)に位置付けられる傾向は一致しています。私はこの図を初めて見た時、感銘を受けると同時に、ある種の慄然とした感情を覚えました。「この学問は、この答えに辿り着くまでに一体どれほどの犠牲を払ってきたのだろう?」という考えが脳裡を去来したのです。事実、ルネサンス以前の西洋医学ではガレノスが絶対的権威として、数百年もの間「ピラミッドの頂点」に君臨してきたのですから、学問の発展によって価値観の顛覆が成し遂げられたのは確かです。
私が学生時代に殊に不満だったのは、同定結果の信頼性が、標本そのものよりも、むしろ同定を行った人物を基にして判断されていることでした。もちろん、その分類群の専門家が検討した標本は正しく同定されている可能性が高いでしょう。しかし、尤もらしいことが真実とは限りません。どれだけ博識で、人格的にも優れた学者が調べたからといって、そもそも当時用いられた技術には限界があったかもしれません。二百年前の顕微鏡に、現代の微分干渉顕微鏡と比してどれほどの性能が期待できるでしょうか?
近年、分子生物学的手法が分類学に取り入れられた結果、標本からDNAを抽出して塩基配列を決定するという、先人の同定結果を検証するための新たな手段が生まれました。私はMinらの2014年の論文[1]を読んで衝撃を受けました。この論文では、韓国の国立樹木園などに収蔵されているヌメリイグチ属のきのこ117標本をDNA分析で再検討したところ、何と半数近い51標本が誤同定されていたのです。それも、ある種Aが常に別の種Bに誤同定されている、というような単純な図式ではありませんでした。この論文のFig.2(再検討前後の同定結果を矢印で結んだフローダイアグラム)はさながら「誤同定曼荼羅」の様相を呈していますが、いかに従来の形態に基づく同定が不正確なものであったかを浮き彫りにしています。日本のハーバリウム標本についても、同様の手法を適用すればこのような結果にならないとは言い切れないでしょう。
近年の技術革新により、きのこの分類体系が大きく変化したことは注目を集めますが、その一方でそれ以前の知見の多くが「誤り」に成り果てた、あるいは再検討を行えばそのことが判明しうる、という現実はほとんど顧みられることがないように思います。しかし、未だ遷延する権威主義はその現実を見つめる眼差しを曇らせます。ある図鑑で昔の学者の同定を誤同定と断じたところ、読者から高名な先生に対して無礼だと批判があったという話を聞きましたが、蓋し短見と言わざるを得ません。旧来の価値観を超克し、同定という行為を明確にサイエンスの俎上に載せるためには、医学における診断との向き合い方に範を取り、客観性と再現性を追究する方向性が必要ではないかと感じます。次回の記事ではその具体的手段について議論する予定です。
[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206787/

1988年生。2014年4月IMIC入職。安全性情報部所属。
学生時代には菌類分類学を専攻。現在は業務の傍ら、アマチュア菌類愛好家(マイコフィ
ル)として、地域のきのこの会等で菌類の面白さを伝える"胞子"活動を行う。
夢は地球上の全菌類の情報を網羅した電子図鑑を作ること。
第17回「Mycologist needs buddy/body.」
2024.03.26 Tue /
第16回「ふわふわとがっちりの狭間で」
2023.07.06 Thu / 中島 淳志
第15回 「generation」
2023.01.11 Wed /
第14回:「i am Naturalist」
2022.06.03 Fri / 中島 淳志
第13回:「想い」が背を押す
2021.11.30 Tue / 中島 淳志
第12回:saturation
2021.05.12 Wed / 中島 淳志
第11回:雲と安楽椅子
2020.11.04 Wed / 中島 淳志
第10回:無免行路
2020.01.07 Tue / 中島 淳志
第9回:フロンティアの空白地図
2019.10.01 Tue / 中島 淳志
第8回:憧憬のクライテリア
2019.07.08 Mon / 中島 淳志
第7回:同定は「先ず解より始めよ」?
2019.05.28 Tue / 中島 淳志
第6回:ハイスループット・フィールド・フェノタイピング
2019.04.25 Thu / 中島 淳志
第5回:きのこ×ヴァリアンス
2019.03.26 Tue / 中島 淳志
第4回:きのこ×ディスタンス
2019.02.26 Tue / 中島 淳志
第3回:根拠に基づくきのこ採集(EBM)
2019.01.22 Tue / 中島 淳志
第2回:命懸けの同定
2018.12.26 Wed / 中島 淳志
第1回:序論
2018.11.13 Tue / 中島 淳志



